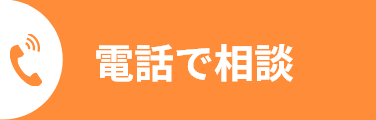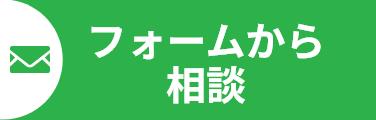2025.05.23 (金)
税務調査が入りやすい法人の特徴とリスクとは?指摘されやすいポイントを税理士が徹底解説

目次
法人の経営者様や経理担当者にとって、しっかり確定申告しているつもりでも「税務調査」は避けたいと感じるものではないでしょうか。
精神的なプレッシャーだけではなく、実地調査へ向けた準備や調査対応だけで大きな負担になります。
本記事では、税務調査が入りやすい法人の特徴と、調査において指摘されやすいポイントを税理士が徹底解説します。
税務調査に入られる確率とその目的
法人の税務調査とは、国税局や税務署などの徴税機関が法人の申告内容に誤りがないか確認するための調査です。
調査を受けるとなると「税務署に疑われているのか?」と思ってしまいますが、ある面ではその可能性もあります。
まずは税務調査に入られる確率を国税庁が発表したデータから明らかにし、税務調査の意義について知ることにしましょう。
法人が税務調査に入られる確率
国税庁が発表している「令和5年度における法人税の申告事績の概要」によれば、令和5事務年度の法人税申告件数は317万6千件となっています。
それに対して同事務年度に実施された法人税等の調査件数は、5万9千件となっており(国税庁「令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要」による)、調査に入る確率は約1.86%(おおよそ53社に1社)と、想像以上に高い水準です。
法人の税務調査の目的と種類
税務調査の目的は、表向きには「公正な税負担の実現を目指して行われるもの」ですが、実際のところは課税漏れとなっている税金を発見することです。
税務調査には大きく分けて「強制捜査」と「任意調査」の2種類があり、近年は自主的な是正を促す「簡易な接触」というケースも増えています。
一般的に税務調査といわれているものは、そのほとんどが国税通則法第34条の6第3項および第131条の規定にもとづき実施される任意調査です。
任意調査では事前に通知されることが一般的で、調査の2~3週間前に連絡が入ります。
予告なく国税局査察部が行う強制捜査は、実施されるケースが限られているので、一般的な税務調査のほとんどは任意調査であり、強制調査は例外的なケースです。 「任意」となっていますが受忍義務(納税者は正当な理由がない限り、税務調査に応じなければならない義務)があるため、拒否したり正当な理由なく必要書類を見せなかったりすると刑事罰を科される可能性があります。
税務調査に入られる法人の特徴
税務調査は数十社に1社の割合で実施されますが、基本的に税務署は管轄エリア内の対象法人に順次調査を実施していると思っておきましょう。
ただ、実際には税務調査に入られやすい法人には特徴があり、ここから説明するような法人は用心が必要です。
近年の税務調査対象のピックアップにはAIが活用されており、より傾向が鮮明になっていくものと思われます。
売上の変動が激しい
法人の売上は景気などに左右されるものですが、売上の変動が大きすぎると調査対象になりやすくなります。
また売上規模が大きい法人ほど申告内容の誤りによる追徴課税額が大きくなるので、税務署の注目度が高いといえるでしょう。 もちろん理由がはっきりしているなら問題ないのですが、調べられる可能性が高まるのは確かです。
同業他社と比較して利益率が低い
税務署(国税庁)は、様々な企業の決算内容を把握しており、業種・企業規模ごとの詳細なデータを分析しています。
税務署は同業他社との比較を重視する傾向があり、売上規模が似たような法人に比べ利益率が低い法人を調査したがる傾向がみられます。 税務当局は、同業種であれば企業努力で利益率が一定水準に収れんするものだと見られがちなので、業界他社の情報は知っておくべきかもしれません。
不自然な利益水準が続いている
一般的に法人の決算は1年間事業を継続した結果ですが、毎期のようにプラスマイナスゼロに近いような数字が続いていると、税務署は利益調整を疑います。
偶然そのような業績が続いているケースでも、調査対象に上がる可能性は高まるでしょう。
過去に税務調査で追徴課税を受けた
過去に税務調査を受けた結果、申告漏れや誤りを指摘され追徴課税を受けた法人は、その後も税務調査の可能性が高いままです。
特に重加算税の対象となる申告漏れがあったようなケースでは、数年以内に税務調査があると考えておきましょう。
特定の業種に当てはまっている
国税庁は税務申告における不正が多い業種を把握しており、そのような業種の法人であれば調査の可能性は高まります。
具体的には現金取引の多い業種ほど不正が多く、飲食業や風俗業、廃棄物処理業などは税務調査が多い業種です。
また国税庁の発表によれば、「漁業、水産養殖」「機械修理」「自動車・同部品卸売」が不正発見割合の高い業種だとされています。
消費税の還付申告をした
国税庁は不正を用いた消費税の還付申告を重点調査項目と位置付けており、消費税の還付申告をした場合にはその内容を細かくチェックしています。
少額であっても、還付申告は税務署のチェック対象になりやすいため、正確な資料と根拠の提示が重要です。
もちろん国税庁がいう「架空の課税仕入れ計上」「輸出免税制度の悪用」といった不正はなくても、消費税の還付申告は目立ってしまいます。
税務調査で指摘されやすいポイント
税務調査で指摘されやすいポイントは事業規模によって異なりますが、ここでは中小法人を対象に解説します。
当然「故意になされた行為」は論外として、ここからピックアップすることが指摘されがちな事項です。
売上・仕入の計上時期
法人経理では、発生主義で収支を把握し申告しなければならないので、売上や仕入の計上時期には注意が必要です。
売上が発生しているにも関わらず未入金だからといって計上していなかったり、先払いの仕入を損金経理していたりしていれば、必ず指摘されるでしょう。
売上や仕入の計上時期のずれだけであれば良いのですが(良くはありませんが)、売上の完全な計上漏れや、仕入の架空計上は確実に発覚し悪質な行為とみなされます。
税務調査では、不正が見逃されることはないと思っておくべきです。
在庫・棚卸資産
社内で行われる実地棚卸は、収支内容に大きな影響を与えるので税務調査で必ず確認されます。棚卸作業は外部から確認できないので、決算時の利益調整に用いられやすい傾向があり、税務調査ではチェックされるものと考えておきましょう。
建設業の未成工事支出金などの計上も注意ポイントで、売上計上としっかり対応しているのか確認が必要です。
人件費と源泉所得税
役員報酬や従業員の給与などの人件費についても注意が必要で、しっかり処理しているつもりでも現物給与や利益供与などが給与認定されることがあります。
また、人件費に関しては不正が多いため実態がある支払なのかチェックされ、架空人件費か否か深掘りされる点には注意が必要です。
それ以外でも代表者の親族に支払われている役員報酬・給与は、税務調査で否認される事例が多いので、損金として認められるのか顧問税理士へ相談しておきましょう。
交際費・福利厚生費
交際費や福利厚生費は、小規模法人では代表者の私的支出が入りやすいと見られがちなので、損金計上には注意が必要です。交際費は領収証があるだけでは経費として認められない可能性があり、私的な支出ではないのか反面調査も頻繁に実施されています。
また、福利厚生費も役員や一部の社員だけを対象とした支出だと経費として認められません。
消費税の経理処理
インボイス制度の導入で注目度が上がった消費税ですが、法人の税務調査では必ず消費税に関する内容がチェックされます。
課税取引なのか不課税あるいは非課税なのかは当然として、個別対応方式における用途区分にも注意しましょう。 特に課税売上割合の高くない法人にあっては、誤りによる追徴課税額が大きくなるので、正しい経理処理は重要なポイントです。
グループ間取引
資本関係のあるグループ会社だけではなく、実質的なグループ関係にある法人間の取引も利益調整に使われがちです。グループ間での貸付や費用按分、役務提供なども、実態に基づいた価格設定がされていない場合には指摘を受けるリスクがあります。 決算期の違う法人間で利益の移転を行うような行為は、税務調査によってあっけなく見破られてしまいます。
これは損失隠しも同様の行為と見なされるため、軽視しないことが重要です。

まとめ
正しく経理処理や税務申告を行っていても、税務調査を受ける可能性は誰にでもあります。大切なポイントは、決算終了後に経理処理や税務解釈に誤りがないか確認することで、そこにこそ顧問税理士の価値があります。また、経営者自らが税務調査に関する基礎的な理解を持っておくことで、担当者任せにせずリスクを事前に察知することも可能です。
税務調査に備える最善の方法は、日頃から正確な経理処理と税務判断を積み重ねることです。税理士に定期的に相談し、決算後のチェック体制を整えることで、余計なリスクや不安を回避できます。
税務調査に関して不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ねください。
TEL:0586-48-5507
FAX:0586-64-6644
コラムの内容は、国税庁等の公式見解を示すものではありません。詳細は顧問税理士にご相談ください。当コラムの活用において生じた損害の一切の責任は負いかねます。