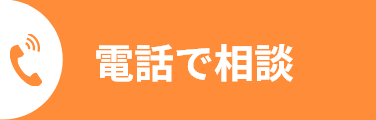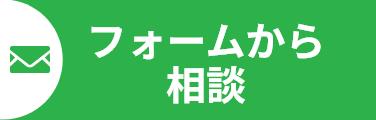2025.11.07 (金)
税務署が把握する富裕層の「資産の動き」:調査対象になりやすい人の特徴と選定の裏側

目次
相続税の税務調査は、申告を済ませた相続人にとって最大の不安要素の一つです。税務調査が行われる確率は、他の税目と比較して圧倒的に高く、調査が入れば高額な追徴課税を支払うリスクがあります。しかし、税務署は無作為に調査対象を選んでいるわけではありません。
税務署は、故人(被相続人)が亡くなる以前からその資産状況を詳細に把握しており、提出された申告書と照らし合わせて、申告漏れや不正が疑われる事案を効率的に抽出しています。特に多額の資産を保有する富裕層については、その資産の形成経緯や移動が厳しくチェックされます。
本コラムでは、税務署が持つ強力な情報網の仕組みと、税務調査の対象として「選ばれてしまう」人の具体的な特徴について、国税庁の最新統計を踏まえて詳細に解説します。
税務署の目と情報網:KSKシステムの活用とデータマッチング
税務署がなぜ申告漏れを発見できるのか、その最大の理由は、納税者情報を一元管理する「KSKシステム(国税総合管理システム)」の存在にあります。
人が亡くなると、死亡届の情報が法務省を経由して国税庁に通知され、税務署は速やかに死亡の事実を把握します。その後、KSKシステムを通じて、被相続人の生前の資産情報が自動的に照合されます。
このシステムには、以下のような情報が蓄積されています。
• 収入源: 毎年の所得税の確定申告データや給与データ。
• 高額な取引履歴: 不動産や高級車などの高額商品の購入履歴。
• 金融資産: 株式の取引履歴や国債の保持者情報など。
• 固定資産: 市区町村役場から提供される固定資産税評価額の情報(不動産の保有状況)。
税務署はこれらのデータを基に、被相続人の収入、家族構成、生前の資産内容から遺産総額の「予想」を立てます。この予想額と、実際に提出された相続税申告書の内容を比較し、申告額が予想額と比べて明らかに少ない場合、税務調査の優先的な対象としてチェックされることになります。
調査対象に選ばれる「金額の基準」—富裕層への重点化
相続税の税務調査について、法律上「いくら以上で必ず調査が実施される」という明確な基準は存在しません。しかし、実務上、財産の規模が大きいほど調査対象となる可能性が高くなる傾向があります。
特に、財産総額が2億円から3億円を超えるケースでは、税務署による調査の優先度が上がる傾向にあると指摘されています。これは、金額が大きい事案ほど、申告漏れや評価誤りがあった場合の追徴税額が大きくなり、税務署の調査効率が高くなるためです。
実際、実地調査1件あたりの申告漏れ課税価格(令和5事務年度)は平均3,208万円に上り、追徴税額は平均859万円と高額です。富裕層の相続では、申告漏れが発覚した際のペナルティ(追徴税額)も高額になりやすいため、税務署は重点的に調査対象としています。
また、富裕層の相続財産には、土地、非上場株式、美術品など評価が難しい資産が含まれることが多く、これらの評価が適正に行われているかを入念にチェックする必要があるという側面もあります。
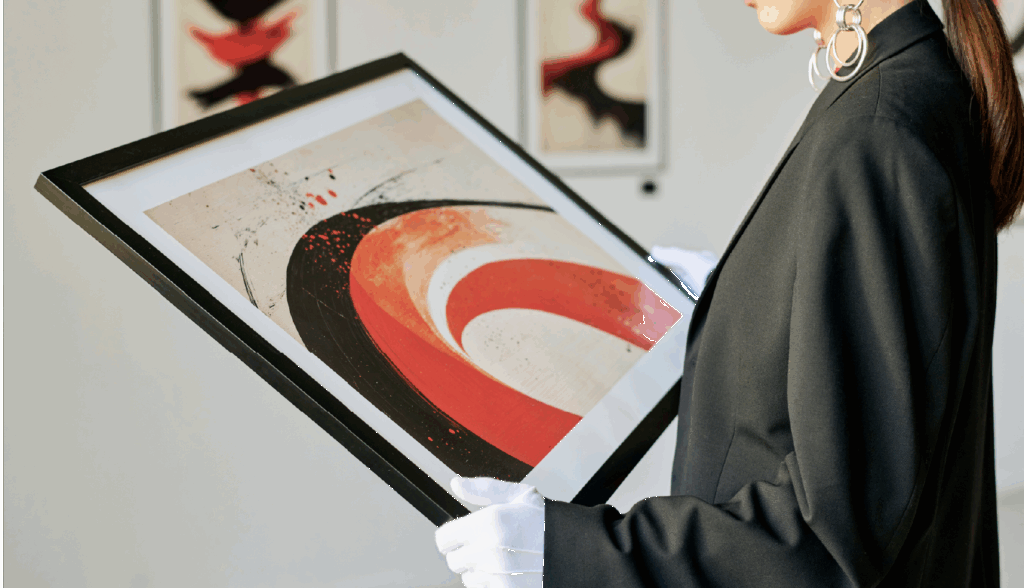
申告漏れの「シグナル」:税務署が特に注目する高リスク事案具体的な流れと場所
金額が大きいという基準のほかに、申告内容や被相続人の行動パターンにおいて、税務調査の「シグナル」となりやすい具体的な特徴がいくつかあります。
税理士に依頼せず「自己申告」している人
相続税の申告は専門的な知識が必要であり、提出書類は第1表から第15表まで15種類以上存在します。
相続税の申告において、税理士が関与する割合は85%を超えているのに対し、所得税の税理士関与率は約20%にとどまります。申告書には税理士の名前を記入する欄がありますが、ここが空欄の場合、「専門知識を持たない人が自己申告した」と判断され、申告内容に誤りがあってもおかしくないとして調査対象になりやすい傾向があります。専門的な知識不足による財産評価や控除の適用ミスが生じやすいと疑われるためです。
金融資産の割合が極端に高い人
相続財産のうち、金融資産(現金・預貯金等)を多く相続した場合、不動産を多く相続した場合と比較して、税務調査が入りやすい傾向があります。
その理由として、土地などの不動産は評価方法に解釈の余地があるため、申告漏れを指摘するのが難しい側面がある一方、現金や預貯金は絶対的な基準があるため、申告漏れを簡単に追徴できると調査官の立場から考えられるからです。
実際に、令和5事務年度の申告漏れ相続財産の金額の構成比を見ると、現金・預貯金等が最も大きな割合(44.1%)を占めており、件数ベースでも2,590件と最多です。
無申告であると疑われる人
相続税の申告義務があるにもかかわらず申告をしていない無申告事案は、納税者の税に対する公平感を著しく損なうため、国税庁は資料情報の収集・活用により、積極的な把握に取り組んでいます。
税務署は、生前の所得税申告書などから、故人が賃貸物件や不動産を所有していたことを把握しています。これらの情報から申告が必要だと見込まれる人には、相続開始後6~8ヶ月を目安に「相続税についてのお尋ね」が郵送されます。これに回答がない、または申告がなされない場合、税務調査が実施されます。
無申告事案に対する実地調査の結果、令和5事務年度の非違割合(申告漏れが指摘される割合)は88.8%123億円に上り、公表を始めた平成21事務年度以降で最高を記録しています。このことからも、無申告者への調査の厳しさが増していることがわかります。
名義預金やタンス預金の疑いがある人
税務調査では、被相続人本人だけでなく、親族(配偶者や子、孫など)の預貯金口座も過去5年から10年程度さかのぼって調査されます。
• 名義預金:名義は家族であっても、被相続人が資金を提供し、通帳や印鑑を管理し、名義人が自由に利用できない状態の預金は、実質的に被相続人の財産(名義預金)とみなされ、相続財産として課税対象となります。特に、収入が少ない相続人の口座に残高が多い場合は、名義預金や生前贈与を疑われる可能性が高まります。
• タンス預金(多額の現金):税務署は、KSKシステムや法定調書などから、被相続人の生前の収入状況に基づき、おおよその現金のストックを把握しています。申告された預貯金と、把握している現金のストックが大きく乖離している場合、「現金隠し」を疑われ、注視されることになります。
海外資産や海外取引がある人
近年、納税者の資産運用が国際化していることに対応し、国税庁は海外資産の把握に注力しています。
税務署は、租税条約等に基づく情報交換制度、特にCRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)100万円を超える海外送金があった場合、金融機関から税務署に「国外送金等調書」が提出されるため、海外に資産を移したとしても、税務署は情報を把握しています。
令和5事務年度における海外資産関連事案(海外資産が存在するもの、被相続人等が国外居住者であるもの、外資系金融機関との取引があるもの等)に対する実地調査件数は947件に上り、海外資産に係る申告漏れ課税価格は62億円でした。海外資産を持つ富裕層は、その所在や移動履歴を明確にし、適正な申告を行うことが不可欠です。
まとめ:税務調査リスクを避けるための専門家活用
相続税の税務調査対象となるかどうかは、資産規模だけでなく、申告内容の正確性、資産構成(金融資産の割合)、そして税理士関与の有無といった複数の要因によって決まります。
税務署が持つ情報網は非常に強大であり、申告書のわずかな不備や、故人の生前の資金の流れの不自然さから、調査の糸口を掴まれてしまいます。
税務調査のリスクを極限まで下げるためには、相続税申告に強い専門税理士に依頼することが最も有効な対策です。専門税理士であれば、不動産の評価を適正に行い過大評価を防ぐとともに、名義預金や過去の贈与についても証拠の有無を確認し、税務署に指摘されないよう万全の対策を講じることが可能です。
不安な点がある場合は、相続税の専門的な知識と豊富な実績を持つ税理士に早めに相談し、正確で信頼性の高い申告書を作成することが、将来の追徴課税という金銭的・精神的負担を避けるための最善策となるでしょう。

税務調査に関して不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ねください。
TEL:0586-48-5507
FAX:0586-64-6644
コラムの内容は、国税庁等の公式見解を示すものではありません。詳細は顧問税理士にご相談ください。当コラムの活用において生じた損害の一切の責任は負いかねます。