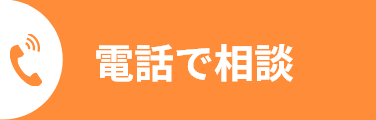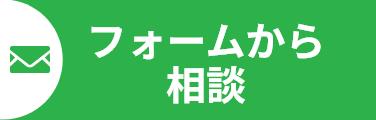2025.09.12 (金)
中小企業でよくある税務調査の指摘事項トップ5:知らないでは済まされない重要ポイント

目次
税務調査は、企業や個人事業主にとって避けられない可能性のあるイベントです。近年、国税庁はAIの活用やオンライン照会制度の導入などにより、税務調査を効率化・高度化させており、その結果、申告漏れ所得金額や追徴税額は過去最高を記録しています。特に中小企業や個人事業主が税務調査で指摘されやすいポイントを事前に把握し、適切な対策を講じることが極めて重要です。
ここでは、中小企業や個人事業主が税務調査でよく指摘される傾向にある5つのポイントとその対策について解説します。
申告漏れ所得(特にネット取引、富裕層、無申告者)
税務調査において最も基本的な指摘事項の一つが、申告漏れ所得です。国税庁はAIを活用して効率的に調査を行っており、申告漏れ所得金額の総額は過去最高を記録しています。特に以下の層が重点的に調査されています。
• インターネット取引を行っている個人
シェアリングエコノミーやデジタルコンテンツ、ネット通販、アフィリエイト、暗号資産(仮想通貨)などの取引を行う個人に対し、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。令和5事務年度では、インターネット取引を行う個人への実地調査件数は1,226件、暗号資産取引を行う個人へは535件実施され、1件当たりの追徴税額はそれぞれ319万円、662万円に上ります。
• 富裕層
有価証券や不動産の保有額が高い個人、経常所得が特に高額な個人、海外投資を積極的に行っている個人など「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化を念頭に積極的な調査が行われています。富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は707万円と、所得税の実地調査(特別・一般)全体の275万円に比べ2.6倍となっています。
• 無申告者
無申告は、納税者に強い不公平感をもたらす悪質な行為と見なされ、的確かつ厳格に対応されています。資料情報の収集・活用を図り、実地調査だけでなく簡易な接触も活用して積極的に調査を実施しています。所得税無申告者に対する実地調査1件当たりの申告漏れ所得金額は2,590万円、追徴税額は417万円と、それぞれ所得税の実地調査全体の約1.9倍、1.5倍となっています。
【対策】
全ての収入を正確に記帳し、申告することが大前提です。特にネット取引や副業による収入は忘れがちですが、税務署はSNSやウェブサイトの情報も確認しています。銀行口座への入金など、資金の流れはオンライン照会制度により税務署に把握されやすくなっているため、不透明な取引は避けるべきです。
消費税の不正還付申告・不適切な経費計上
消費税に関しても、追徴税額の総額が過去最高を記録しており、重点的に調査されています。
特に還付申告には厳格な審査が行われ、申告内容に疑義がある場合には還付を保留し、実地調査などが行われます。
• 不正還付申告
仕入れの水増しや輸出売上げの過大計上などにより、消費税の還付を不正に受ける手口が問題視され、取り締まりが厳しくなっています。
・インボイス制度への対応
2023年10月から始まったインボイス制度により、より厳格な経理処理が求められています。インボイスの保存義務を怠ったり、会計処理の判断を誤ったりすると、余計な消費税を負担させられる可能性があるため注意が必要です。
• 無申告者への調査
消費税の無申告者に対する追徴税額も過去最高の214億円に上り、1件当たり追徴税額も274万円と過去最高を記録しています。
また、経費の妥当性についても厳しくチェックされます。税務調査官は、帳簿の不備や、申告所得と生活費との間に大きな乖離がある場合、意図的な所得隠しを疑うことがあります。
【対策】
消費税の還付申告を行う場合は、関連資料を完璧に整理し、説明できるように準備しましょう。インボイス制度に対応した適切な経理処理を徹底し、仕入れや経費の計上においては、それが事業活動に直接関連するものであることを明確に証明できる書類を必ず保管してください。個人的な支出と事業経費を明確に区別し、曖昧な部分がないように注意が必要です。領収書や出納帳を「破棄」したと回答すると、意図的な隠蔽と見なされ、重加算税の対象となる可能性があるため、「紛失」などの言葉を選ぶなど、回答にも注意が必要です。
海外取引に関連する問題(適正価格、源泉徴収漏れ)
経済社会の国際化に伴い、海外取引を行っている中小企業も増えています。国税庁は、有効な資料情報の収集に努め、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人に対し、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を実施しています。
• 海外投資
海外の不動産や証券などへの投資、海外での預貯金等の蓄財が含まれます。海外投資を行っている富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は1,290万円と、所得税の実地調査(特別・一般)全体の約4.7倍に達しています。
• 取引価格の適正性
日本よりも税率が低い国へ利益を移転したり、通常ではありえないような価格で取引したりするような場合には、申告漏れが指摘されます。
• 源泉徴収漏れ
外国法人への支払い時に源泉徴収が必要な場合があるにもかかわらず、その義務を怠るミスが多く見られます。例えば、借入金の利子やソフトウェアの使用料を外国法人に支払う場合、また事務所のオーナーが外国人や外国法人に替わった場合などです。
【対策】
海外取引がある場合は、商品やサービスの取引価格が適正であるかを常に確認してください。外国法人への支払いがある場合は、源泉徴収の要否や税率(租税条約による特例の有無)を事前に確認し、適切な手続きを行うことが不可欠です。国際的な情報共有が進んでいるため、隠蔽は困難と考え、透明性のある取引を心がけましょう。

帳簿・書類の不備、意図的な資料破棄
税務調査では、提出された申告書だけでなく、その根拠となる帳簿や書類の整備状況が重視されます。これは、経理処理の信頼性を示すバロメーターとなるためです。
• 資料の不備・不足
領収書や出納帳などの重要資料が不足している場合、税務調査官は意図的な隠蔽を疑うことがあります。特に「資料を破棄しました」と回答すると、「意図して捨てた、隠した」と解釈され、重加算税の対象となる可能性があります。「紛失してしまった」という表現であれば、重加算税にはならないケースがあるため、言葉選びには注意が必要です。
•預貯金等情報のオンライン照会
国税庁は金融機関の預貯金情報をオンラインで照会する制度を本格運用しており、迅速かつ広範囲な調査が可能になっています。対応金融機関は大幅に増加し、将来的にはクレジットカード会社や資金決済事業者にも拡大する方針です。これにより、調査官は事前に社長やその家族の事業外口座の情報を把握し、内容について指摘してくることがあります。
【対策】
全ての取引について、領収書、請求書、契約書などの証拠書類を適切に保管し、整理整頓を徹底してください。電子帳簿保存法に対応し、デジタルデータも適切に管理しましょう。説明がつきにくい預金の入出金は極力避け、事業用口座と個人用口座を明確に分けることが望ましいです。万が一、書類が見つからない場合は「紛失」と伝え、「破棄」という言葉は避けるようにしましょう。
不明瞭な資金の流れと生活費との矛盾
中小企業や個人事業主の場合、事業用資金と個人用資金の区別が曖昧になりがちです。これが税務調査で大きな問題となることがあります。
• 生活費と申告所得の乖離
税務調査官は、納税者の生活状況や家族構成から推定される生活費と、申告されている所得金額との間に大きな乖離がないかを確認します。例えば、申告所得が300万円なのに、生活費が年間600万円かかっていると判明した場合、税務署は「申告していない所得があるのではないか」と疑いを持ちます。
•調査官の質問への安易な回答
税務調査官は、納税者の回答を「ピン留め(事実を固定すること)」しようと様々な質問をします。例えば「売上は100%口座に入金されますか?」という質問に「100%口座です」と答えた後に、現金売上の証拠を突きつけられた場合、「隠していた」と見なされるリスクがあります。
【対策】
事業用口座と個人用口座は厳密に使い分け、事業に関連しない個人の支出を事業経費として計上しないようにしてください。自身の生活費を把握し、申告所得とのバランスが極端に崩れていないか確認することも重要です。 税務調査官との会話では、安易に断定的な言葉(「100%」「絶対」など)を使わず、「そう認識しています」「だと思います」といった表現を用いることで、事実を固定されることを避け、後で解釈の余地を残すようにしましょう。

税務調査に臨む際の心構えと専門家の活用
税務調査は、納税者にとって精神的な負担が大きいものです。しかし、上記の傾向と対策を理解し、準備を怠らなければ、不必要な追徴課税や重加算税を回避できる可能性が高まります。
税務調査官は、調査の冒頭10分で納税者の信頼性を判断していると言われています。服装や部屋をきれいに保ち、事業概況の質問には嘘をつかず、誠実に対応することが、その後の調査をスムーズに進める上で重要です。質問に対しては即答できるよう、日頃から事業内容や経理処理について整理しておくことが望ましいでしょう。
もし税務調査の連絡が来た場合、税務の専門家である税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、税務調査の立会いを代行し、経理処理や経費の妥当性を税法に基づいて説明することで、追徴課税のリスクを最小限に抑えることができます。また、想定される質問に対するリハーサルを行うことで、納税者が自信を持って対応できるようサポートしてくれます。税務調査は「突然」ではないため、日頃からこれらの対策を講じておくことが、安心して事業を続けるための鍵となります。
税務調査は、まるで緻密な探偵劇のようです。調査官は、申告書という「表の顔」だけでなく、帳簿や証拠書類、さらには納税者の言動や生活状況といった「裏の顔」までを照らし合わせ、矛盾点や隠された事実を探し出そうとします。AIやオンライン照会という現代の高性能な「探偵道具」を駆使しているからこそ、納税者側も「事実」と「解釈」を冷静に見極め、プロの「弁護士(税理士)」と共に、論理的かつ誠実に対応することが、円満な解決へと繋がるのです。
税務調査に関して不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ねください。
TEL:0586-48-5507
FAX:0586-64-6644
コラムの内容は、国税庁等の公式見解を示すものではありません。詳細は顧問税理士にご相談ください。当コラムの活用において生じた損害の一切の責任は負いかねます。