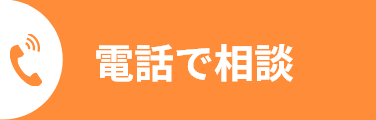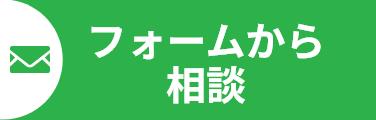2025.09.05 (金)
【知らぬ間に「最重要ターゲット」に?】税務調査で狙われる要注意業種と今すぐできる対策~AIとオンライン照会が強化する調査のリアル~

目次
納税者が自ら所得を計算し申告・納税を行う「申告納税制度」の下、適正に税金を納めている大多数の納税者にとって、無申告や不正な申告は強い不公平感をもたらします。このため、国税庁は無申告者に対して的確かつ厳格な対応を講じており、彼らは税務調査における「最重要ターゲット」とされています。
近年、国税庁はAI(人工知能)の活用を本格化させ、申告漏れが疑われる事案の選定を効率化しています。これにより、令和5事務年度(令和5年7月~令和6年6月)の所得税の調査等における追徴税額の総額は1,398億円と過去最高を記録しました。このAIによるリスクスコア判定は、令和7年7月からは相続税申告に対しても全国一律で導入される予定です。
また、情報収集の面でも、金融機関の預貯金情報をオンラインで迅速かつ広範囲に取得できる「預貯金等情報のオンライン照会制度」が令和3年10月から本格運用されており、対応金融機関は当初の37行から令和6年度には431行にまで増加し、国内金融機関の約7割以上が対応済みです。この制度導入後、照会件数は飛躍的に増加し、令和3年度の28万件から令和6年度には835万件に達しています。実際の税務調査の現場では、調査官が事前に社長やその家族の事業外口座まで照会にかけ、内容を指摘してくるケースも報告されており、課税庁側が迅速かつ広範囲に情報を取得できる環境が整っていることを示しています。
このようなAI活用や情報収集の高度化に加え、納税者宅等に臨場して行う「実地調査」だけでなく、文書や電話、来署依頼による面接などの「簡易な接触」も積極的に活用され、調査が実施されています。令和5事務年度の所得税の調査等合計件数は60万5千件、消費税の調査等合計件数は12万件に上ります。
今回は、特に税務調査で申告漏れ所得が高額になりやすい「要注意業種」に焦点を当て、無申告者が直面する厳しい現実、そしてそこから是正への道筋を探ります。

所得税・消費税無申告者が直面する厳しい現実
税務調査で無申告が発覚した場合の影響は甚大です。
• 所得税無申告者への調査の厳しさ
令和5事務年度において、所得税の無申告者に対して5,274件の実地調査(特別・一般調査)が実施されました。この調査による1件当たりの申告漏れ所得金額は2,590万円であり、所得税の実地調査(特別・一般)全体の平均1,370万円に比べ、約1.9倍も高額になっています。追徴税額についても、1件当たり417万円と、実地調査(特別・一般)全体の平均275万円の約1.5倍に上り、その総額は220億円に達しています。
• 消費税無申告者への調査の厳しさ
消費税の無申告者に対する調査は特に厳しさを増しており、令和5事務年度には7,827件の実地調査(特別・一般調査)が実施されました。
消費税無申告者への追徴税額の総額は過去最高の214億円を記録し、1件当たりの追徴税額も274万円と過去最高を更新しています。これは消費税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たり平均158万円と比較して約1.7倍にもなります。 また、会社に利益が出ていない赤字法人であっても消費税や源泉所得税について調査されることがあるため、油断は禁物です。消費税の還付申告者への調査も厳格化しており、令和5事務年度には910件の実地調査が行われ、1件当たりの追徴税額は162万円に上ります。還付申告をする際には必ず税務調査が入ると考えておくべきでしょう。不正還付申告は「国庫金の詐取ともいえる悪質性が高い行為」として、警察当局との連携も強化され、刑事責任追及も行われることがあります。
【要注意業種】税務調査で申告漏れ所得が高額な上位10業種
国税庁の公表資料によると、令和5事務年度における事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種は以下の通りです。これらの業種は、税務調査において特に重点的に見られる可能性が高いと言えるでしょう。
1. 経営コンサルタント: 申告漏れ所得金額 3,871万円(追徴税額 1,040万円)
2. ホステス、ホスト: 申告漏れ所得金額 3,654万円(追徴税額 507万円)
3. コンテンツ配信: 申告漏れ所得金額 2,381万円(追徴税額 436万円)
4. くず金卸売業: 申告漏れ所得金額 2,068万円(追徴税額 683万円)
5. ブリーダー: 申告漏れ所得金額 2,028万円(追徴税額 459万円)
6. 焼き鳥: 申告漏れ所得金額 1,657万円(追徴税額 427万円)
7. 太陽光発電: 申告漏れ所得金額 1,625万円(追徴税額 119万円)
8. 内科医: 申告漏れ所得金額 1,621万円(追徴税額 408万円)
9. スナック: 申告漏れ所得金額 1,616万円(追徴税額 326万円)
10. 西洋料理: 申告漏れ所得金額 1,517万円(追徴税額 288万円)
これらの上位業種の中には、「経営コンサルタント」「ホステス、ホスト」「コンテンツ配信」ネットを介したビジネスを行っている個人に対して、積極的に調査を実施していると明言しています。シェアリングエコノミーやデジタルコンテンツ、ネット通販などの新分野の経済活動に係る取引を行っている個人への実地調査は1,226件に上り、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,432万円、追徴税額は319万円となっています。また、暗号資産(仮想通貨)等取引を行っている個人に対する調査も強化されており、1件当たりの追徴税額は662万円と、所得税の実地調査(特別・一般)全体の275万円に比べて約2.4倍という高額な結果が出ています。
これらの業種に従事する方々は、税務当局からの注目度が高いことを認識し、より一層の適正な申告・納税を心がける必要があります。
無申告が招く重いペナルティと長期的な影響
税務調査で不適切な経理処理や脱税が明らかになった場合、過去3年間分の申告内容だけでなく、税務署員が脱税の事実を確認した場合は、調査の対象期間が最大で過去7年間分まで延長される可能性があります。 また、追徴課税に加え、以下のような重いペナルティが課されます。
• 過少申告加算税:期限内に申告したが税額が少なかった場合。
• 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合。
• 重加算税:悪質性が高いと判断された場合。追加で納める税額に35%または40%が加算され、結果的に税金が約1.8倍になるとも言われています。
最悪の場合、脱税として刑事罰を受けるおそれもあります。 さらに、自身の事業だけでなく、反面調査として取引先等にも税務調査が入る可能性があり、それによって取引先との関係悪化や信頼低下につながるリスクもはらんでいます。これは事業継続に深刻な影響を及ぼしかねません。
今すぐできる対策と賢い対応策
このような厳しい状況を避けるためには、自発的かつ適正な申告・納税が大前提です。しかし、もし既に無申告の状態であったり、税務調査が実施されることになったりした場合には、以下の点に注意し、賢く対応することが不可欠です。
税務調査での「言葉選び」の重要性
税務調査官は、納税者の言葉尻を捉え、意図的な隠蔽(重加算税の対象)があったと認定しようとすることがあります。例えば、領収書や出納帳などの資料がない際に「破棄しました」と答えると「意図して捨てた、隠した」とみなされ重加算税の対象となる可能性がありますが、「紛失してしまいました」「そう認識しています」「事実」は一つでも「解釈」は無数にあるという考え方に基づきます。納税者の生活費が申告所得を明らかに上回る場合などに矛盾を指摘されても、「当時、自分は正しいと認識していた」という時点のズレを利用して、故意ではないことを主張することが重要です。税務調査の基本的なスタンスは、言われたことに対して最小限に回答することです。
税務調査の「初動対応」と「印象管理」
税務調査は「最初の10分で勝負が決まる」とも言われています。調査官の信頼を得るためには、服装や部屋をきれいに整えることが重要です。特に、税務調査の冒頭に行われる事業概況に関する質問には、聞かれたら即答できるよう、事前に準備しておくことが肝要です。即答することで、調査官に「正直者である」という良い印象を与え、その後の調査がスムーズに進む可能性が高まります。調査官はSNSやホームページなども確認して情報収集しているため、聞かれる内容には十分注意が必要です。身振り手振りや目線も調査官に与える印象に影響するため、意識的な準備も有効です。
信頼できる税理士の活用
税務調査において、税理士の存在は不可欠です。税理士に依頼する最大のメリットは、追徴課税を回避または最小限に抑えられる可能性が高まることです。税理士は税法に基づき経費の妥当性を論理的に説明し、税務署との協議・交渉を代行することで、納税者の精神的ストレスを大幅に軽減できます。
経験豊富な税理士は、税務署員がチェックするポイントや想定される質問事項を把握しており、これらを踏まえた入念な準備やリハーサルを行うことで、税務調査を円滑に進めることができます。無申告や期限後申告にも対応可能であり、限られた時間の中でも適切な準備と対策を施して調査に臨むことが可能です。
また、製造業、建設業、飲食業、小売業、システム業など、企業の業界・業種を問わず、適切な対応が期待できます。税務署から連絡が来た後の依頼でも対応してくれる税理士事務所もあります。

まとめ
国税庁のAI活用やオンライン照会制度の拡大により、税務調査は年々効率化・深度化しており、無申告者はこれまで以上に厳しい調査に直面する時代となりました。特に、申告漏れ所得が高額な上位業種として挙げられた「経営コンサルタント」「ホステス、ホスト」「コンテンツ配信」など、個人事業主やネット取引を行う事業者は、税務当局から重点的に scrutinize されていることを認識すべきです。
無申告行為は、納税者全体の公平性を損なうため、的確かつ厳格な対応がとられます。もし、ご自身の申告に不安がある方や既に無申告の状態である方は、事態が悪化する前に、速やかに税理士などの専門家に相談し、適切な申告・是正への道筋を立てることが最も賢明な選択と言えるでしょう。税務調査は、プロの知識と経験を借りることで、そのリスクを大きく軽減できるのです。自らの申告内容を正確に把握し、不明点があれば専門家を頼ることで、安心して事業に専念できる環境を整えることが、何よりも重要です。
これは、羅針盤なしで嵐の海に出るようなものです。適切な羅針盤(税理士の知識と経験)があれば、嵐を乗り越え、安全な港にたどり着くことができるでしょう。
税務調査に関して不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ねください。
TEL:0586-48-5507
FAX:0586-64-6644
コラムの内容は、国税庁等の公式見解を示すものではありません。詳細は顧問税理士にご相談ください。当コラムの活用において生じた損害の一切の責任は負いかねます。