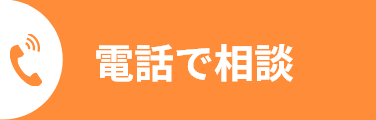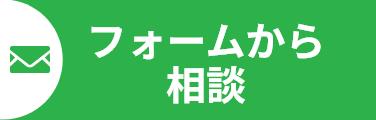2025.07.24 (木)
令和最新版!税務調査のリアルと対策

目次
近年の税務調査は、国税庁の積極的な取り組みと技術の進化により、その実態が大きく変化しています。以前にも増して効率的かつ厳格になり、納税者にはより一層の理解と対策が求められるようになっています。今回は、最新の税務調査の傾向と、それに対する効果的な対策について解説します。
進化する税務調査の現状:AIとデータ活用
国税庁は、税務調査の選定にAI(人工知能)を本格的に活用しており、申告漏れの事例をAIに学習させることで、調査対象の選定を効率化しています。
その結果、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月)における所得税の申告漏れ所得金額の総額および追徴税額の総額は過去最高を記録しました。所得税・消費税を合わせた「調査等」による追徴税額は1,398億円(前事務年度1,368億円)と、こちらも過去最高を記録しています。
この「調査等」は、納税者宅等に臨場して深度ある調査を行う「実地調査」と、原則として臨場せずに文書や電話、来署依頼による面接で申告内容を是正する「簡易な接触」に分けられます。
令和5事務年度においては、「実地調査」の件数、非違件数、追徴税額の総額および1件当たりの追徴税額が増加傾向にあり、また「簡易な接触」の申告漏れ所得金額の総額および1件当たりの申告漏れ所得金額も増加しています。
具体的には、「調査等」の合計件数は60万5千件(前事務年度63万8千件)で、うち申告漏れ等の非違があった件数は31万1千件(同33万8千件)でした。
このうち、実地調査は4万8千件(同4万6千件)行われ、特別調査・一般調査が3万7千件、着眼調査が1万件となっています。実地調査による追徴税額は1,066億円(同1,015億円)に上り、1件当たりでみると224万円(同219万円)となっています。
申告漏れ所得金額は「調査等」の合計で9,964億円(同9,041億円)に達し、簡易な接触による申告漏れ所得金額は4,448億円(同3,448億円)と大きく増加しています。
また、国税庁は税務調査時の資料収集において、預貯金等情報のオンライン照会制度を令和3年10月から本格運用しており、これにより金融機関(銀行、信用金庫、証券会社、生命保険会社など)からの預貯金情報を、従来の紙ベースの照会よりも劇的に迅速かつ広範囲に取得することが可能になりました。
この制度は税務調査の効率化に大きく貢献しており、オンライン照会に対応する金融機関は制度開始当初の37行から令和6年度には431行にまで増加し、国内の金融機関の約7割以上が対応済みです。
令和7年度には対応金融機関を450行とすることを目指しており、今後はクレジットカード会社や資金決済事業者にも対象を拡大する方針が示されています。
この照会件数は年々増加の一途を辿っており、令和3年度の28万件から令和4年度の263万件、そして令和6年度には835万件と大幅に増加しています。
実際の税務調査の現場では、調査官が事前に経営者やその家族の事業外口座まで詳細に照会し、説明が難しい入出金についてピンポイントで指摘することが可能になっています。
課税庁側が迅速な情報収集対応ができる環境が整っているため、納税者側は説明がつきにくい預金の入出金は極力避けるなど、疑わしい行為は避けるべきであると強く考えられます。
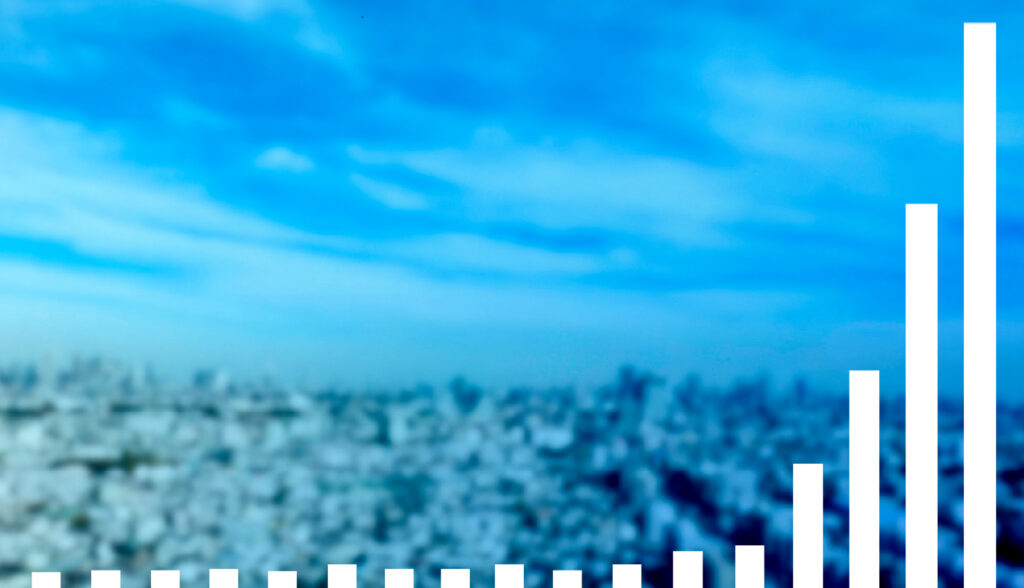
さらに、国税庁は調査機会が限られる相続税への対応を強化するため、令和7年7月からは相続税申告に対してもAIによる「リスクスコア判定」が全国一律で導入される予定です。
これは、過去の調査実績から申告誤りの傾向を分析し、提出された申告書データのリスクをスコア化することで、効率的に調査対象を選定するものです。
これにより、税務調査が必要となるような事案を取りこぼさないよう体制が整えられています。令和5事務年度に実施された相続税の実地調査などによる追徴税額は857億円に上り、これは平成28事務年度以降で最高額を記録しています。
今後はAIによるスコアリングが選定要素として加わることで、さらに効率的な税務調査が進められることが予測されます。
特に狙われやすい重点調査分野
AIとデータ活用が進む中で、国税庁は特定の分野に重点を置いて調査を強化しています。
富裕層および海外取引・海外投資を行っている個人
有価証券や不動産などの大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人、海外投資等を積極的に行っている個人など、富裕層に対しては、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に、積極的な調査が実施されています。
富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は707万円であり、これは所得税の実地調査(特別・一般)全体の平均275万円と比較して2.6倍に達します。
特に、海外投資等を行っている富裕層に対する調査では、1件当たりの追徴税額が1,290万円と、所得税の実地調査(特別・一般)全体の平均275万円の約4.7倍に達しており、極めて高額な追徴税額となっています。国税庁は、国外送金等調書や国外財産調書、租税条約に基づく情報交換制度、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、国際的な情報連携を深めながら積極的に調査を実施しています。
海外に関連会社がある場合、取引価格が適正かどうか、利益を税率の低い国に移転していないか(移転価格税制の観点)などが重点的に確認されます。また、海外の取引先への支払いにおいて、外国法人への支払いにおける源泉徴収漏れがよくあるミスとして指摘されており、特に注意が必要です。
例えば、借入金の利子やソフトウェアなどの使用料を外国法人に支払う場合にも源泉徴収が必要になることがあります。都内の不動産でオーナーが外国人(外国法人)に替わったことで源泉徴収が必要になった事例もあり、納税者が意図せず源泉徴収義務を怠っていたケースが見られます。
外国法人に対するすべての支払いが源泉徴収の対象ではないものの、支払いを行う前には必ず源泉徴収の有無を経理に確認させ、支払い相手国との租税条約の確認、そして税務署への事前の手続きを忘れないよう指示しておくことが不可欠です。
インターネット取引を行っている個人
インターネット上のプラットフォームを介して行われるシェアリングエコノミー等新分野の経済活動や、暗号資産(仮想通貨)などの取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。
新分野の経済活動には、民泊やカーシェアリング、クラウドソーシング、配達代行業などのシェアリングビジネス、アプリ作成・配信や有料メルマガなどのデジタルコンテンツ、ネット通販やネットオークション、ドロップシッピング、アフィリエイトなどのネット広告が含まれます。
暗号資産取引を行っている個人に対する調査では、1件当たりの追徴税額が662万円と、所得税の実地調査(特別・一般)全体の平均275万円の約2.4倍に上ります。
令和5事務年度における高額な申告漏れ所得金額が見つかった事業所得を有する個人の上位10業種には、インターネットを介したビジネスである「ホステス・ホスト」(申告漏れ所得金額3,654万円)や「コンテンツ配信」(同2,381万円)が新たにランクインしており、ビジネス様態の多様化が調査対象にも顕著に反映されていることが伺えます。
無申告者
無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、国税庁は的確かつ厳格に対応していく必要があるとしています。
こうした無申告者に対しては、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しています。所得税の無申告者に対する1件当たりの申告漏れ所得金額は2,590万円と、所得税の実地調査(特別・一般)全体の平均1,370万円の約1.9倍です。
また、消費税の無申告者への消費税の追徴税額の総額は214億円(前事務年度198億円)、1件当たりの追徴税額も274万円(同260万円)と、いずれも過去最高を記録しています。
消費税
法人に利益が出ていなくても消費税の税務調査は行われることがあり、油断は禁物です。特に、仕入れの水増しや輸出売上げの過大計上など、不正な還付請求が悪質な事案として厳しく取り締まられています。
国税当局としても、税金を納税者に対して還付するときには特に慎重になるため、消費税の還付申告をするときには、必ず税務調査が入ると考えておくべきでしょう。
令和5事務年度の消費税(個人事業者)の調査等合計の追徴税額は423億円(前事務年度396億円)と、こちらも過去最高を記録しており、実地調査の1件当たり追徴税額も135万円(同132万円)に増加しています。また、令和5年10月から始まったインボイス制度により、経理処理の厳格さが一層求められるようになりました。
インボイス(請求書や領収書)の保存義務を怠ったり、会計処理の判断を誤ったりすると、会社は余計な消費税を負担させられることになりかねないため、経理部門においては一層の注意が必要です。消費税の不正還付申告に対しても厳格な審査・調査を実施しており、1件当たりの追徴税額は162万円となっています。

まとめ
現代の税務調査は、AIとビッグデータによって強化され、特定の分野に焦点を当てた、より精密な「デジタル監査」へと進化しています。納税者としては、常に透明性のある経理処理を心がけ、疑わしい行為は避けることが大前提です。
税務調査は、まるで緻密なパズルを解くようなものです。国税庁はAIという強力な道具と膨大な情報というピースを使って、納税者のパズルが正確に組まれているかを確認しています。もしパズルに隙間や誤りがあれば、そこから追徴課税というペナルティが生じます。日頃からピース(帳簿や記録)をきちんと整理し、いざという時に備えることが大切です。
税務調査に関して不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ねください。
TEL:0586-48-5507
FAX:0586-64-6644
コラムの内容は、国税庁等の公式見解を示すものではありません。詳細は顧問税理士にご相談ください。当コラムの活用において生じた損害の一切の責任は負いかねます。