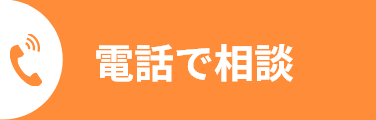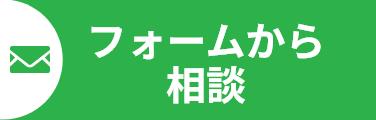2025.11.14 (金)
税務調査で最も指摘される「見落とし財産」:現金・預貯金と名義預金の危険性

目次
相続税の税務調査は、納税者にとって大きな負担と不安を伴うものです。一度調査が行われると、約9割近い確率で申告漏れが指摘されるという現実があり、その際の追徴税額は1件あたり平均859万円にも上ります(令和5事務年度)。
では、税務調査において、いったいどのような財産が最も見落とされ、指摘の対象となっているのでしょうか。国税庁の統計データは、その答えを明確に示しています。それは、土地や家屋といった不動産ではなく、身近でありながら最も隠蔽しやすい「現金・預貯金等」です。
本コラムでは、税務調査の現場で最も問題となる「現金・預貯金等」の申告漏れの実態と、特に注意すべき「名義預金」や「タンス預金」の危険性、そして税務署がどこまでその資産の流れを把握しているのかについて詳細に解説します。
申告漏れ財産で群を抜く「現金・預貯金等」の割合
税務調査により申告漏れが指摘された財産の構成比を見ると、「現金・預貯金等」が他のどの財産よりも圧倒的に高い割合を占めていることが分かります。
統計に見る現金・預貯金等の突出
令和5事務年度(2023年7月~2024年6月)の申告漏れ相続財産の金額の構成比を見ると、現金・預貯金等が44.1%と最大の割合を占めています。この割合は前事務年度(41.0%)からも増加しており、申告漏れの中心が現金・預貯金にあることが示されています。 件数ベースで見ても、現金・預貯金等は2,590件と、土地(825件)や有価証券(485件)を大きく上回る最多の指摘事項となっています。
なぜ預貯金は狙われやすいのか
相続財産には、土地や家屋などの不動産も含まれますが、これらと比較して金融資産が調査に入られやすい傾向があります。
その理由として、土地などの不動産は、評価方法に解釈の余地があり、評価の仕方が財産額に影響を与える側面があるため、調査官の立場からすると指摘が難しいという側面があります。
一方で、現金や預貯金は絶対的な基準があり、その有無や残高が明確です。そのため、税務署の調査官から見て「申告漏れを見つけやすく、簡単に追徴できる」という判断になり、調査対象として優先度が高くなるのです。
税務署が把握する「資金の流れ」の深層
納税者が「タンスにしまっておけばバレない」「家族名義なら大丈夫」と考えがちなのに対し、税務署は強大な情報網を活用して、被相続人(亡くなった方)とその親族の資金の流れを広範かつ長期間にわたって把握しています。
調査は親族名義の口座も含め10年分を遡及
税務調査では、被相続人名義の通帳の入出金だけでなく、親族(配偶者や子、孫など)の通帳も調査の対象となります。
一般的に、相続発生時に税務署は銀行や証券会社に対して5年から10年程度さかのぼって残高照会や取引の出し入れを確認するといわれています。金融機関は、通常、請求日から過去10年分の取引履歴を保存しており、税務署はその範囲内で情報開示を求めることができます。
これは、故人の生前の収入状況に対して、親族の口座に不自然な入金がないか、あるいは大きな資金移動がないかを確認し、名義預金や生前贈与が適切に申告されていたかを検証するためです。
KSKシステムによる現金のストックの把握
税務当局は、納税者情報を一元管理するKSKシステム(国税総合管理システム)などを活用し、被相続人の生前の給与、報酬、不動産の売買、高額な買い物、税金の納付状況など、様々な法定調書情報を総合的に管理しています。
この情報網のおかげで、税務署は被相続人の生活費や出費を差し引いた、おおよその現金のストックを把握することが可能です。そのため、申告された預貯金の額と、税務署が把握しているはずの現金のストックが大きく乖離している場合、「現金隠し」(タンス預金)を疑う大きな根拠となります。
海外送金も完全に把握されている
国内の金融資産だけでなく、海外への資産移転についても税務署は把握しています。1回あたり100万円以上の海外への送金があった場合、金融機関から税務署へ国外送金等調書が提出されます。このため、「海外にお金を置いておけば見つからない」ということはありません。また、国税庁はCRS情報(共通報告基準)などの租税条約に基づく情報交換制度を活用し、海外資産の保有状況の把握に努めています。

税務調査で最も危険な二大「隠蔽資産」
現金・預貯金等の申告漏れの中でも、特に税務調査で追及されやすいのが「名義預金」と「タンス預金」です。
隠れた相続財産「名義預金」の危険性
名義預金とは、名義上は配偶者や子、孫など他人になっていますが、実際には被相続人(亡くなった方)が資金を提供し、通帳や印鑑を管理していたため、実質的に被相続人の財産とみなされる預金です。
税務調査で名義預金が疑われる典型的なパターンは以下の通りです。
・資金の源泉: 預金の資金が被相続人の口座から振り込まれている。
・収入との不一致: 名義人(例:専業主婦や学生)の収入や資産形成の根拠がないにもかかわらず、多額の預金残高がある。
・管理の実態: 通帳や印鑑の管理を被相続人が行っていた、または名義人がその預金を自由に利用した形跡がない。
税務署は税務調査の前や調査中に、被相続人以外の名義での取引がないか金融機関に照会しています。名義預金と認定された場合、それは相続財産として課税対象となり、申告漏れとして追徴課税や罰則のリスクが高まります。
現金隠しと疑われる「タンス預金」の追及
自宅に多額の現金を保管する、いわゆるタンス預金も、税務調査で注視される申告漏れ財産の典型です。
特に調査官が追及するポイントは、被相続人の死亡直前の多額の現金引き出しです。過去3年から5年の間に、1回につき概ね50万円以上の金額を引き出している場合、その使い道について追及されます。これは、引き出された現金を相続財産に計上せず隠しているのではないか、あるいは名義預金として預け替えているのではないかを確認するためです。
税務調査当日には、調査官は自宅の金庫やタンス、書類の保管場所など、貴金属や貴重品を保管している場所の現物確認を求め、実際にどれくらいの現金が残されているかを把握しようとします。被相続人の現金のストックを事前に把握している税務署に対し、不自然な現金減少を説明できなければ、追徴課税は免れません。
税務調査を回避するためにできること
相続税の税務調査で最も指摘される財産が現金・預貯金である以上、この分野での対策が極めて重要です。
申告前に徹底的な財産の洗い出しと証明
税務調査のリスクを回避するためには、申告前に被相続人の財産をすべて洗い出し、正確な申告を心がけることが大前提です。特に見落としがちな財産としては、「現金(タンス預金やへそくり)」「名義預金」「亡くなられた方との金銭の貸し借り」「生前贈与された財産」などが挙げられます。
家族や親族の口座も含め、過去の資金移動をチェックし、大きな入出金については使途を証明できる記録(契約書、領収書、振込記録など)を揃えておくことが不可欠です。
相続税専門税理士の活用
相続税申告におけるミスや見落としを防ぐためには、相続税申告に強い専門税理士に依頼することが最も有効な対策となります。
専門税理士は、税務調査で指摘されやすいポイント(名義預金の判断、不動産の適正評価など)を熟知しており、申告書の正確性を高めます。また、税理士が関与することで、書面添付制度を活用するなどして税務署からの信頼度が上がり、調査リスクを大幅に軽減できる可能性があります。
もし税務調査の連絡が来てしまった場合でも、税理士が立ち会うことで、調査官の質問の意図を理解し、不適切な回答や不利な誘導尋問を避けることが可能となり、結果的に追徴税額の軽減につながる可能性が高まります。 申告漏れを指摘され、高額な追徴課税というリスクを負わないためにも、相続の準備段階から専門家による慎重なチェック体制を構築することが重要です。

税務調査に関して不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ねください。
TEL:0586-48-5507
FAX:0586-64-6644
コラムの内容は、国税庁等の公式見解を示すものではありません。詳細は顧問税理士にご相談ください。当コラムの活用において生じた損害の一切の責任は負いかねます。