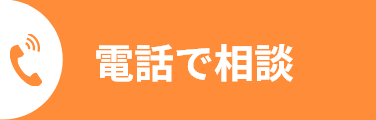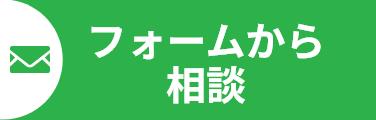2025.10.31 (金)
知っておきたい相続税の税務調査の流れと時期:事前準備と調査官からの質問例

目次
相続税の申告を終えた後も、多くの相続人が抱える最大の不安、それが税務調査です。国税庁の統計が示す通り、相続税の税務調査は約20%(5件に1件)という高い確率で実施され、調査が行われた事案の約9割(令和5事務年度で84.2%)で申告漏れなどの非違が指摘されています。
そして、指摘を受けた際の1件あたりの追徴税額は平均859万円に上ります。 この高いリスクを避けるためには、税務調査がいつ、どのように行われ、調査官が何を調べようとしているのかを事前に把握し、万全の準備を整えておくことが不可欠です。本コラムでは、相続税の税務調査(実地調査・臨宅調査)が始まる時期や具体的な流れ、そして調査官から聞かれる質問の具体例と対策について解説します。
相続税の税務調査が行われる時期と種類
調査の最盛期は「申告から1~2年後の夏から秋」
相続税の税務調査が行われる時期には、明確な傾向があります。一般的に、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後)から1~2年後の間に行われることが多いとされています。
特に、7月下旬から11月頃が税務調査の最盛期(ピーク)といわれています。これは、税務署の事務年度が6月末で替わり、7月初旬は人事異動などで煩雑な時期を過ぎた後、比較的調査に集中できる期間が続くためです。 ただし、必ずしもこの時期に限られるわけではなく、3年後以降に連絡がある場合もまれにあります。
調査の大部分を占める「任意調査」
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類がありますが、相続税の調査のほとんどはこの任意調査に該当します。
任意調査は、納税者の協力のもとで行われる調査であり、税務署は調査対象者(相続人や税理士)に対し、事前に調査を行いたい旨の連絡を入れ、調査日の日程調整が行われます。通常、この連絡は調査予定日の1~2週間前(1週間から10日ほど前)に入ります。
「任意」と名前がついていますが、正当な理由なく拒否することは原則的にできず、強硬に拒否すると、悪質な不正が疑われる場合に限られる「強制調査」に発展する可能性があるため、注意が必要です。
また近年は、実地調査(臨宅調査)を行う一方、文書や電話、来署依頼による面接で申告漏れなどを是正する「簡易な接触」という手法も活用されています。令和5事務年度においては、この簡易な接触件数は前事務年度比で125.2%の大幅な増加となっています。
税務調査(実地調査)の具体的な流れと場所
実地調査(臨宅調査)は、調査官が被相続人の自宅などに訪問して行う調査であり、一般的な流れは以下のようになります。
調査場所と立ち会い者
調査場所:相続税の調査は、原則として被相続人が生前に生活の拠点としていた自宅で行われることが多いです。ただし、自宅が売却された場合などは、相続人の自宅や、立ち会う税理士の事務所など、話し合いで場所を決めることができます。
立ち会い者:調査には、可能な限り相続人全員の立ち合いが望ましいとされています。これは、調査の結果、追加で納税が必要になった場合、申告漏れでの増額分は相続人全員が負担する義務があるためです。また、税理士を依頼している場合は、必ず税理士も立ち会います。
時間と人数:調査は通常、10時頃に始まり、調査官は2人組(質問係と記録係)で訪問するのが基本です。調査期間はたいてい1日で終了しますが、内容が多岐にわたる場合や問題が生じた場合は、数日間にわたることもあります。
調査当日の具体的な流れ
調査当日は、午前中に調査官による相続人への聞き取り調査が、午後からは現物確認調査が行われるのが一般的です。
聞き取り(ヒアリング):調査官は、相続人のプロフィールや、被相続人の生前の暮らしぶり、資産形成の経緯、亡くなる前の状況など、幅広い質問をします。
現物確認:質問内容を裏付けるため、通帳や書類の保管場所、金庫の中身などの確認が行われます。
指摘事項への対応:調査終了後、後日(2週間~1ヶ月ほど)税務署から調査結果が伝えられ、申告漏れや誤りがあった場合には、修正申告を求められます。

税務調査の事前準備:当日までに揃えるべき資料と心構え
申告内容の再確認と財産の洗い出し
申告書の再確認:提出した相続税申告書 の控えと、その添付資料、計算根拠となる資料 を用意し、計算ミスや記入漏れがないか再確認します。
財産の洗い直し:特に見落としがちな財産(タンス預金やへそくりなどの現金、名義預金、生命保険金などのみなし相続財産、亡くなる前一定期間内に生前贈与された財産など)がないか、自宅や金庫をよく探して再調査します。
通帳の整理:被相続人の通帳はもちろん、相続人の通帳も調査対象となるため、過去5年〜10年程度さかのぼって確認し、大きな入出金(概ね50万円以上)があった場合には、その使い道を証明できる記録(契約書、領収書など)を確認しておきましょう。
必要な書類の準備
調査当日には、主に以下の書類が求められる可能性があります。
• 相続税申告書の控え
• 遺産分割協議書
• 戸籍謄本(亡くなった方の出生から死亡まで)
• 預貯金通帳や残高証明書
• 不動産の権利証や評価証明書
• 相続人の認印
税理士の立ち会いの重要性
申告を自分で行った場合でも、税務調査の連絡が来た時点で新たに相続専門の税理士に依頼し、立ち会いを依頼できます。税理士が同席することで、調査官の質問の意図を理解し、誘導尋問のような状況を避け、追徴される税額が軽減される事例もあります。
調査官が尋ねる「質問例」と「真の意図」
調査官は、相続財産の申告漏れ(特に金融資産)がないかを確認するために、さまざまな角度から質問を投げかけてきます。何気ない会話のように聞こえても、すべては申告の適正性を確認するためのものです。
調査でよく聞かれる質問と、その背後にある調査官の意図は以下の通りです。
| 質問例 | 調査官の真の意図 |
| 被相続人の生前の職業、趣味は? | 生前の収入源や支出の規模、資産形成の経緯を推測し、申告されている財産額が収入規模に見合っているかを確認している。 |
| 生前に大きな出費があれば、その使途は? | 死亡直前の多額な出金が、相続財産から除外されたタンス預金になっていないか、あるいは意図的な現金隠しがないかを追及している。 |
| 財産は誰が管理していたか、通帳や印鑑の管理状況は? | 名義預金の有無を確認している。家族名義の口座であっても、被相続人が通帳や印鑑を管理・運用していれば、相続財産とみなされる。 |
| 相続人の職業、収入、資産状況は? | 相続人名義の口座に残高が多い場合、その資金源が相続人自身の収入によるものか、被相続人からの名義預金や未申告の生前贈与ではないかを確認している。 |
| 過去に金融機関や証券会社との取引(解約した口座も含む)は? | 申告されていない有価証券の申告漏れがないか、または解約した高額な金融商品が現金(タンス預金)となって残っていないかを確認している。 |
| 被相続人の入院や介護費用は? | 亡くなる前の多額の医療費や介護費用の支払いにより、預金が減少した理由が正当なものかを確認し、不自然な資金の流出がないか確認している。 |
| 貸金庫を持っているか? | 金融機関の口座に現れにくい、貴金属や現金などの隠し財産がないか確認している。 |
調査官からの質問に対し、その場ですぐに答えられない場合は、慌てて不適切な回答をするよりも、事実を確認してから後日回答する方が賢明です。
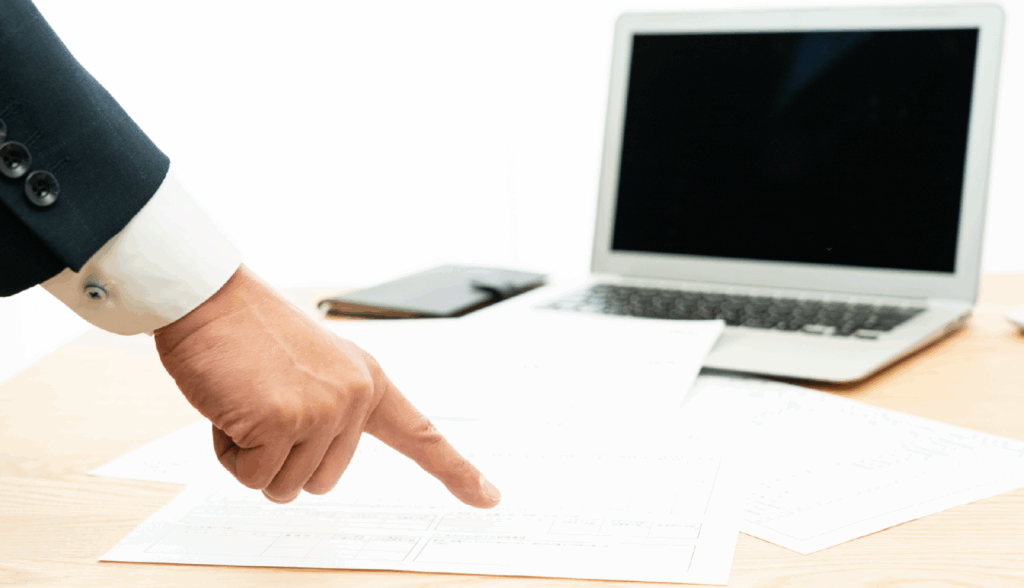
まとめ:万が一に備える専門的サポート
相続税の税務調査は、申告の正確性を確認する重要な手続きであり、その実施率は高く、追徴のリスクも高額です。
調査が行われやすい時期や、調査官が特に注視するポイントを事前に把握し、以下の対策を講じることが重要です。
正確な申告書の作成
見落としや計算ミスがないよう、すべての財産を把握し、正しく申告する。
生前贈与の記録
生前贈与があった場合は、贈与契約書や振込記録など、正当性を証明できる証拠を必ず残しておく。
専門税理士の活用
相続税申告に強い専門税理士に依頼することで、申告内容の正確性を高め、書面添付制度などを活用し、調査リスクを大幅に軽減する。
調査への準備
万が一調査の連絡があった場合は、事前に通帳や関連資料を過去10年分程度整理し、想定される質問への回答を準備しておく。 相続税は複雑な税制であり、税務調査を回避し、追徴課税のリスクを最小限に抑えるためには、相続専門の知識と経験を持つ税理士のサポートを受けることが最も確実な方法です。
税務調査に関して不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ねください。
TEL:0586-48-5507
FAX:0586-64-6644
コラムの内容は、国税庁等の公式見解を示すものではありません。詳細は顧問税理士にご相談ください。当コラムの活用において生じた損害の一切の責任は負いかねます。